常夜の郵便
夜咄 頼麦 作
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この文章の著作権は夜咄頼麦に帰属しますが、朗読についての著作使用権は解放しております。YouTubeでの朗読、声劇、そのほか音声表現活動などで自由にお使いください。
その際、この原作ページのURLを作品などに掲載していただきますよう、お願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「やっと辿り着いた。ここが魔法使いの家ね」
いつもより深い夜の闇にも、だんだんと目が慣れてきました。少女は暗がりに建つ家の前に立ち、今日の出来事を思い返しました。
少女の名前はシャルと言います。束ねた金の髪は、目を見張るような美しさです。いつも元気に走り回っているせいか、貧しい生活でも身体は丈夫でした。
彼女の住む森に囲まれた小さな村では、ここ数年、朝が来ていませんでした。
シャルは幼い頃の陽射しを覚えていますが、まだ小さい子どもたちには記憶がありません。朝を知らない子どもたちは、あまり外で遊ぶこともしませんでした。
たまに雲が晴れても青空はなく、夜空ばかりが続いています。村の人々は小さな木の実や、日陰で育つ野草を食べて暮らし、皆痩せ細っていました。
このままでは作物を育てることができず、生活は苦しくなる一方です。村人はいつも不安にさいなまれ、夜だというのに眠れておりませんでした。
シャルが村を出る数時間前、村の長老のおばあさんが村人たちを集会所に呼んで言いました。
「このままではいけない。朝を迎えるための方法を占おうぞ」
おばあさんは、森に捨てられていたシャルを引き取り、ずっと面倒を見てくれた恩人です。少女は、思いやりに溢れ、村人にも慕われるおばあさんが大好きでした。
おばあさんは、集会所の奥にある大きな水晶の前に座りました。村人たちも、その周りに集まります。おばあさんは、水晶に両手をかざしました。
「おお、これは…」
水晶の中に、ひとりの少女の姿が映り込みました。彼女の姿は力強く、凛とした美しさを持っています。
ぼろぼろの衣服や、風になびく金の髪はもはや神々しいほどでした。少女は村の中心にある噴水の前で、杖を掲げておりました。
「救世主が現れ、村を救ってくれるのじゃ」
おばあさんは水晶を見つめ、嬉しそうに告げました。
突然、水晶の中から眩しい光が溢れ出し、地下室全体を包み込んでいきました。あまりのまぶしさに、村人たちは目をつむります。
やがて、光は一筋にまとまり、村人の後ろの方で聞いていた少女を指しました。
「シャルが救世主だというのか」
おばあさんは少女を見つめて言いました。水晶の中には行く先となる森の暗闇が映されています。
「お前には厳しい旅になるかも知れないが、引き受けてはくれんかね」
村人たちは不安そうな顔をしたり、期待を込めて見つめたりしています。中には心配のあまり、泣き出す人もおりました。
「わかったわ。やってみる」
おばあさんは心当たりがあると言って、森の奥に住む魔法使いのことを教えてくれました。こうして、世界に夜明けをもたらすための旅が始まることになったのです。
シャルはおばあさんに持たされたランプの灯りを頼りに、暗い森の道を歩きました。道と言っても、何年も人が歩いた形跡はなく、荒れ放題のけもの道です。衣服の届かない足首は擦り切れ、ヒリヒリと痛みました。
おばあさんは、魔法使いの家まで半日はかかると言っていました。しかし、シャルは旅の全てを楽しむつもりでした。変わり映えのない日々に飽きていた少女にすれば、滅多にできない大冒険だったからです。
シャルには、水晶に映った美しい少女と、自分とはかけ離れて思えました。元気とは言え、進んで皆の前に出るような性格ではありません。
それでも、親のない自分を優しく見守り、育て上げてくれた村の皆には恩義があります。シャルは心から、自分にできることを成し遂げたいと思っていました。
森に入ってしばらくは、元気なシャルでさえ怖気付いてしまうほどの暗さでした。しかし、心が折れそうになるたび、ランプの灯りが心を温めてくれました。寒い時期であり、虫の少ないことだけが救いでした。
魔法使いの家に近づくと、一寸先まで見えぬほどに闇が深くなります。朝の来なくなった村と魔法使いには、何か関わりがあるに違いありません。
「やっと辿り着いた。ここが魔法使いの家ね」
いつもより深い夜の闇にも、だんだんと目が慣れてきました。少女は暗がりに建つ家の前に立ち、擦れてメッキの剥げたドアノブに手をかけました。
外から見たところ、中はそれほど広くなさそうです。黒みがかった木製の扉がギィィと音を立てます。
「ごめんください…」
中からは誰の反応もなく、声がむなしく響きます。どうやら、魔法使いは留守のようでした。シャルは少し迷いましたが、中に入って魔法使いの帰りを待つことにしました。
そっと中に入ってみると、中は薄暗く、少しだけ湿ったカビの匂いがしました。床を見ると、うっすらホコリが積もっていて、長い間掃除されていないことが分かります。
うず高く積まれた分厚い本の塔があちらこちらに立っているせいでしょうか。外から見た以上に、中は狭く感じました。
玄関から本の塔を倒さないように進んで行くと、突き当たりに暖炉がありました。不思議な紋様の敷物の上で、大きなロッキングチェアが揺れています。シャルは誰もいないのに揺れる椅子を見て気味が悪く感じました。
暖炉の右の壁際には古めかしい机と、背もたれのある椅子がありました。机の上にも、分厚い本が何冊か置かれています。
シャルは本に興味をもって、気になったものをパラパラとめくってみました。見たこともない文字ばかりでしたが、なんだか読める気がします。
少女は本を一度閉じて、最初からじっくり読み始めました。
『魔道入門』と書かれた本の冒頭にはこう書かれていました。
魔法を使うために必要なものは三つある。
一 魔力
二 杖
三 愛
少女はこの文章を読み終えると、小さく呟きました。
「魔力と杖はわかるけれど、愛ってどういうことだろう」
すると突然、背後から声が聞こえました。
「良い疑問だな」
振り返ると、そこにいたのは灰色のローブをまとった老人でした。頭には同じく灰色の三角帽を乗せ、たっぷりとあごひげを蓄えています。いかにも魔法使い、といった風貌でした。
「あの、あなたが森の魔法使いさんですか?」
「そうだが」
「私の名前は…」
「知っている。シャルというのだろう」
「どうして分かったんですか!」
「あの村でつけられそうな名前だ」
少女は首を傾げました。
「それで、何用だ?まさか遊びに来たわけではないだろう」
「はい、実はお願いがあって来たんです」
シャルはこれまでの経緯を話し始めました。
ここ数年、夜が村を覆ってしまっていること。
おばあさんの占いで、夜明けには自分が鍵になると知ったこと。
薄暗い森の中、どうにかここまで辿り着いたこと。
「つまり、お前の村を覆っている夜の闇を払ってほしいということだな」
「そうなんです。どうか、よろしくお願いします」
「断る」
早速の返事に、シャルは驚きました。無愛想ではありますが、きっと引き受けてくれると思っていたからです。
「どうしてですか?」
「わしはお前の住む村に絶望した。共に滅んでしまってもいいと思っている」
そして、驚きの事実を語りました。なんと、世界を夜に染めてしまったのは魔法使い本人だと言うのです。
シャルは魔法使いを見て言いました。
「どうしてそんなことをしたんですか!」
「当然の報いだ」
「…」
シャルは言葉を失いました。優しい村人達に支えられて育ったシャルには、魔法使いの言うことが分かりませんでした。しかし、遥々ここまでやってきて諦めるわけにはいきません。
「魔法使いさん、何か理由があるんですね?」
「なぜ出会ったばかりのお前に理由を話さねばならない」
少女は束の間考え、魔法使いの目を見て言いました。
「私の大切な人たちのため。ここはどうしても退けないの」
魔法使いはじっと少女を見つめ、しばらく目を離しませんでした。そして、深いため息をつきました。
「お前を見ていると誰かを思い出すようだ。いいだろう。かけなさい」
魔法使いは背もたれのある椅子をこちらに向けました。そして、少女が腰掛けるうちに、温かい飲み物を用意して渡してくれました。寒くないように、膝に毛布をかけてくれます。
シャルは、思いがけない魔法使いの行動に少し驚きました。彼は暖炉の前のロッキングチェアに座り、語り始めました。
「何から話そうか…まずは、わしと村との関係を話す必要があるな」
老人は静かに、淡々と、これまであった出来事を語りました。
自分はかつて、村の子供として生まれたこと。
自分だけが魔法を使えるせいで、かつての村人たちから恐れられたこと。
周りの村人だけではなく、家族さえも彼から離れていったこと。
孤独に耐えかねて村を飛び出し、この森で独り、暮らし始めたこと。
それを聞いたシャルは言いました。
「魔法のない世界があったなんて。今では、魔法を恐れる人はいないわ」
「うむ。わしは早すぎたのだな。それに、わしは魔法で人を傷付けたことは一度もなかった。しかし、周りの人間は何か悪い事が起こると全てをわしのせいにした」
「…」
「わしと関わりのある人間が不幸になるならば、わしは初めから居ない方がよかろう」
「…」
「だが、村の中で一人だけ、わしを心配してくれるものがいた。今では村の長老をやっているだろう」
シャルはうつむいて、じっと耳を傾けていましたが、ここで目を上げました。おばあさんが、魔法使いの知り合いだったなんて。初めて聞くことばかりです。
「彼女だけは、魔法の素質を持っていたのだろう。わしの力を知っても離れようとはしなかった。村からここまでの道のりを歩き、物資を届けてくれることもあった。彼女は言った。『あなたは悪くない』と。『あなたが仲間外れにされるなんて間違っている』と。彼女との関わりだけが、長年のわしの支えだった。しかし…」
「…何があったんですか」
「数年前のある日を境に、彼女は来なくなった」
「えっ」
「あれ以来、ずっと会えていない。大方、誰かにそそのかされたのだろう。また独りになった、わしの悲しみは天まで届き、世界から朝を奪ってしまったのじゃ」
「おばあさんは、そんな理由で人を見捨てたりしません!」
「本当にそう思うのか」
「私にはわかります」
「…お前に何がわかるのだ」
目を落とした魔法使いは、どこか寂しげに見えました。
シャルは思いを巡らせました。シャルはおばあさんの優しさを知っています。自分にはもちろん、村の皆にも分け隔てなく接する、大好きで尊敬するおばあさんです。絶対に何か、理由があるはずでした。
「私は孤児で、おばあさんに育てられました。だから、彼女のことはよく知っているつもりです。おばあさんがなんの理由も無くそんな行動をとるとは思えないんです」
魔法使いは目を見開きました。
「魔法使いさんの寂しさも少しだけわかります。私だって独りだったし、今でも独りです。辛くて閉じこもる日もありましたが、自分の思うまっすぐな道を生きてきたつもりです」
「ひよっこが、何を言うておる」
魔法使いは首を振り、身体を少し揺すって、遠い目をしました。ロッキングチェアの手すりに指を滑らせています。言葉はありませんでしたが、シャルは魔法使いに何かが伝わったと感じました。
しばらくの沈黙の後、魔法使いは言葉を紡ぎました。
「ここにお前が来たことも偶然ではないのかも知れんな。彼女はきっと、お前に手一杯だったのだろう。お前が彼女の手紙だというならば、わしもそれに応えねばなるまい」
魔法使いは椅子から立ち上がり、玄関に立てかけた杖を持ってきました。
「これをお前に譲ろう」
「でも、これは大切なものなんじゃ」
「もう必要の無いものだ。受け取りなさい」
シャルは杖を受け取りました。使い込まれた杖は、暖炉の火に照らされて鈍く光りました。魔法使いは言いました。
「その杖には魔力を誘う力がある。お前に魔法の素質があることはわしが保証しよう。その目を見ればわかる。村に帰って杖を掲げ、愛を抱いて念じなさい」
「じゃあ、魔法使いさんも一緒に」
「いいや」
魔法使いは少女の肩に手を置きました。
「わしは孤独を愛して余生を過ごそうと思う。今更皆に合わせる顔もない。愛を受け取り、巡らせることができるお前なら、魔法とも上手くやっていけるじゃろう」
シャルは静かに頷きました。
「さあ、行きなさい。道中気をつけてな」
少女は、おばあさんのランプと魔法使いの杖を頼りに、森の暗闇を歩きました。衣服の裾は茂みに裂かれ、草木を払うたびに髪は乱れます。
村に着く頃には、彼女はぼろぼろでした。しかし、一つの旅を終えた少女は、凛とした力強さを纏っていました。
「シャルが帰ってきたぞー!」
シャルに気づいた村人が叫びました。少女の帰還に気づいた村人たちは、次々に家の扉を開けて出てきました。
シャルが噴水の縁にランプを置くと、村人たちは少女をもみくちゃにしました。
「シャルー!」
「よく帰ったな」
「無事でよかった」
シャルは故郷の温かみに安心して、少し目を潤ませました。しかし、まだやることが残っています。
長老がいちばん後ろからやってきて、シャルの前に立ちました。そして、彼女の抱えた杖を見て言いました。
「その杖は…」
シャルが頷いたのを見て、おばあさんは肩を震わせ、顔を覆って言いました。
「おじいさん、たしかに受け取りました」
シャルは杖を抱き、村の皆を想い、おばあさんを想い、魔法使いを想いました。 そして、杖を掲げました。
杖から一筋の光が立ち上り、夜を晴らしていきます。その光景は、かつて水晶の中に見たあの光景と全く同じでありました。
こうして、世界に朝が訪れました。朝陽が、暗闇に慣れた村の人々の目に眩しく差し込みました。彼らが明るさに慣れるには、しばらくの時間を要しました。
村の住人たちは喜び、感謝の気持ちをシャルに伝えました。少女に経緯を聞いた村人たちは、自分たちの先祖の行いを悔いました。そして、二度と同じ過ちを繰り返さないと誓いました。
今でも、森の小さな村には、杖を掲げる少女の石像が立っています。村人たちは、心優しく勇敢な少女の物語を子孫たちに伝えていきました。
物語を受け取った人々の心には、温かい陽の光が差し込んだのでした。
おしまい
スポンサーリンク
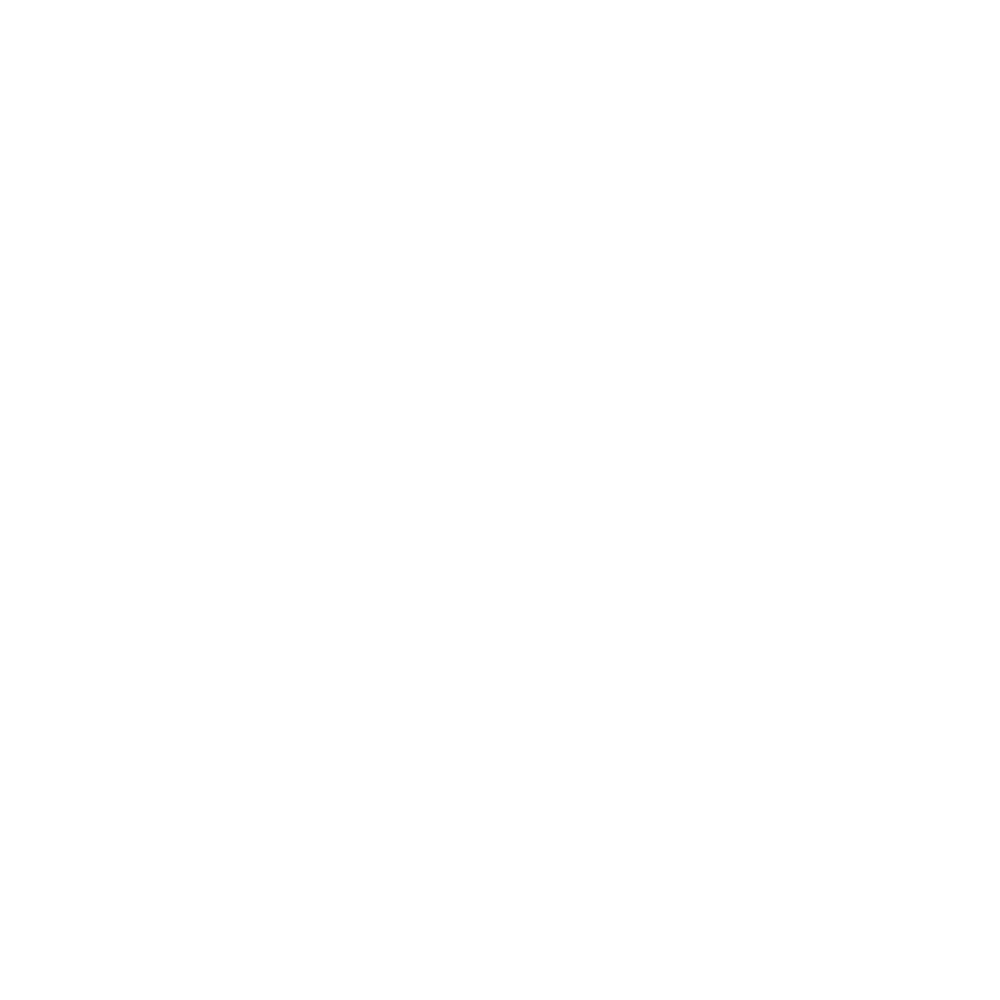








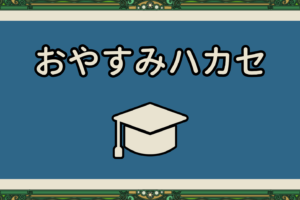


2024年2月11日
一番嫌な事が巡ってくるこの時期が苦手だといつも話されている頼麦さん。
一昨年は覚えてる「さっさと」という詩だった。
やりたいことだけやるために、やることさっさとおわらせる。
昨年の今ごろは何を思ってらしたのかしら?とページを開いてみました。
「常夜の郵便」
そんな苦手な時期にこんなにも素敵な物語を紡いでらした
なんて・・・驚愕。
完成している物語がとても素敵でぐうーっと引き込まれ
読み進むほど惹き付けられて行きました。
お芝居になりそうなStory・・・
発する言葉が見つかりません。
私の貧しい言葉を連ねても蛇足になるだけ。
是非たくさんの人に読んでほしい!!
見逃していた自分が悔しい。
そして、いつの日か頼麦さんの声で聴きたい!!
長編だけれど、可能なら・・・