時雨の名残
夜咄 頼麦 作
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この文章の著作権は夜咄頼麦に帰属しますが、朗読についての著作使用権は解放しております。YouTubeでの朗読、声劇、そのほか音声表現活動などで自由にお使いください。
その際、この原作ページのURLを作品などに掲載していただきますよう、お願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
そうか、君は、やり切ったんだね。
鋭い熱が日中の気温上昇を予感させる朝。
住宅のつくる影に身を隠すように、一羽の蝉が横たわっていた。
節ばった脚を器用に折りたたみ、左右対称の形をつくっている。
その端正な姿に、棺桶の中で腕や脚を整えた故人を思い出す。
あの人も、この蝉のような充実感を持って、亡くなることができたのだろうか。
そうで、あってほしい。
私は蝉の側にあった石段を一瞥し、黒ずみを避けるようにして腰を下ろした。
まだ汚されておらず、澄んでいる空気を胸いっぱいに吸い込む。
乾燥で少しかすれた喉がヒュウと音を立てた。
気づけば、毎朝叩きつけるようにして降っていた蝉時雨も静かになったものだ。
鼓膜の震えを感じ取れるほどの大合唱に嫌気がさしていたが、静かになってみれば、少し寂しい。
皆、この蝉のように、どこかで横たわっているのだろうか。
誰に看取られる訳でもなく、ただ、静かに最期を迎えている。
それで、いいじゃないか。
彼らは、全うしたのだ。
風が吹く。
静止していた空気は流れ、流れた空気は葉を撫でる。
つられて見上げた空は柔らかく、赦しを投げてくれていた。
見上げたことで、水が溢れて頬を伝う。
ああ、いい空だ。
いい、空だ。
全ては、繋がっている。
あの人を看取っていなければ、この地には居なかったし、この蝉の美しい姿に足を止めることはなかった。
足を止めて腰を下ろさなければ、空を見上げて泣くこともなかった。
全ては、繋がっている。
「私も、いつか」
誰にも看取られなくていい。
ただ、静かな充実感を持って、死にたい。
その為に、生きるのだ。
その為に、記すのだ。
両の膝を掴み、地面を押すようにして立ち上がる。
蝉は、そのままにした。
邪魔をしたくなかったのだ。
影は狭くなり、肌が熱に包まれ始めた。
どこかでシャッターの開く音がする。
街は、そろそろお目覚めの時間だ。
一日が始まる。
私の、一日が始まる。
この一日を重ねた先に最期があるのなら。
全ては、繋がっているのなら。
今日は、どのように生きてやろう。
スポンサーリンク
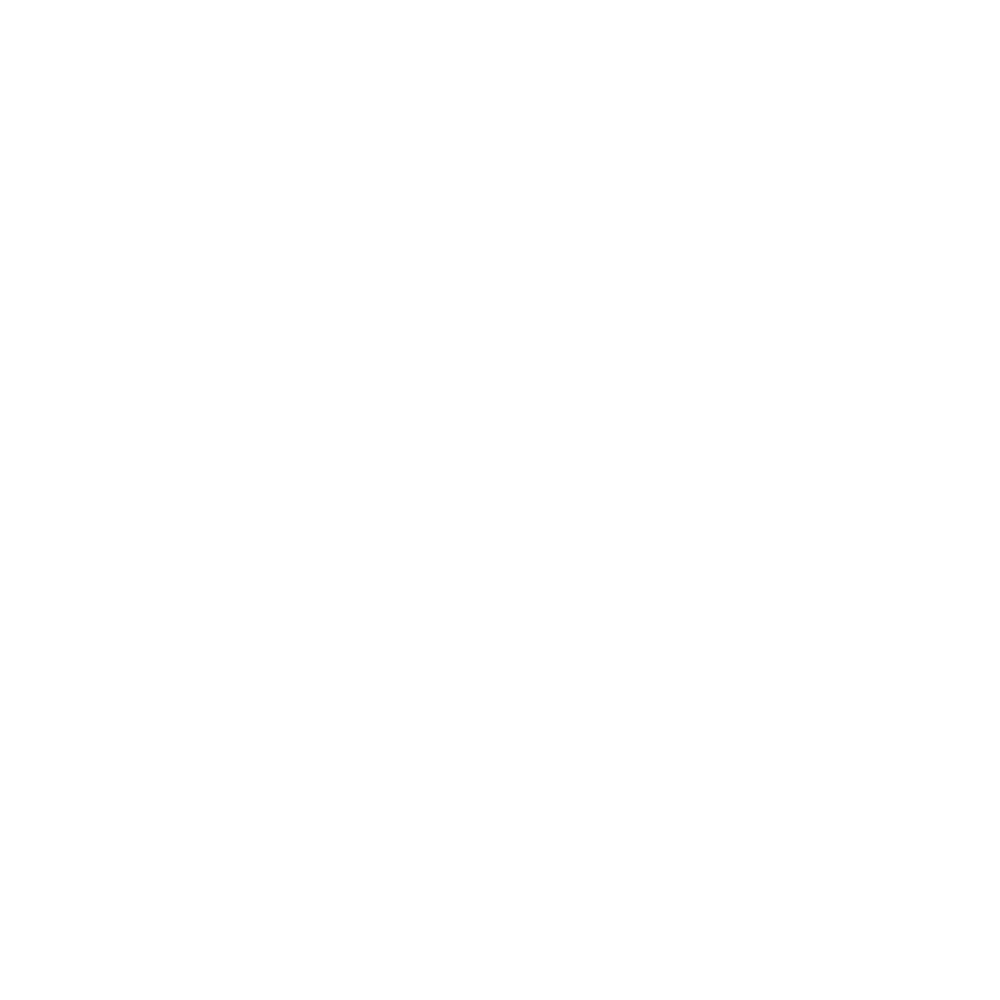





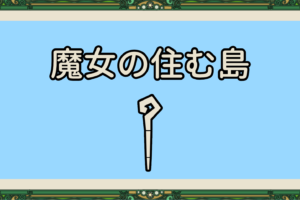



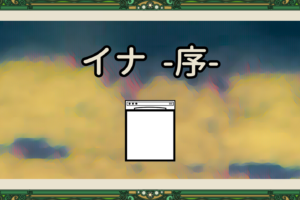

最近のコメント