川原の石
夜咄 頼麦 作
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この文章の著作権は夜咄頼麦に帰属しますが、朗読についての著作使用権は解放しております。YouTubeでの朗読、声劇、そのほか音声表現活動などで自由にお使いください。
その際、この原作ページのURLを作品などに掲載していただきますよう、お願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
夜は、しんとしていました。まるで、深い、深い海の底に沈んでしまったかのように、町は静まりかえっていたのです。健一が、そっと自分の家の戸をあけて外へ出たのは、もう十二時を過ぎたころでありました。
健一の胸には、このごろ、いつも重たい石が一つ、入っているかのようでした。それは、学校の成績が悪いからでもなければ、友だちと喧嘩をしたからでもありません。もっと、わけのわからない、雲のような、霧のようなものが、いつも心のどこかに立ち込めて、晴れる時がなかったのです。
昼の間は、人々の話し声や、往来の騒がしさにまぎれて、いくらかは忘れることもできましたが、こうして独りになると、その重たいものは、ずしりと健一の胸を抑えつけるのでした。
健一は、誰にも気づかれないよう、足音を立てずに家の前の小路に出ました。ひやりとした夜の空気が、頬を撫でます。空を見上げると、磨かれた黒いガラス板に、誰かが銀の砂をまき散らしたかのように、数えきれないほどの星が、またたいていました。その一つ一つの光は、遠い、遠い世界から、何万年という長い旅をして、やっと今、この健一の目に届いているかと思うと、なんだか気の遠くなるような、不思議な気持ちがしたのです。
彼は、あてもなく歩きだしました。足はいつの間にか、町のはずれにある、大きな川の堤防へ向かっていきました。彼の履いている運動靴の底が、固い土の道をギュッ、ギュッと擦る音が、やけに大きく響きました。時折、風がヒュウと吹いて、道ばたの枯れ草の葉を鳴らしました。それは、まるで年を重ねた老人が、かすれた声でため息をついているかのようでした。
やがて、健一の目の前に、黒々とした堤防が見えてきました。彼は、その斜面を静かにのぼっていきました。登り切って見下ろすと、川が一本の黒い帯のように、どこまでも、どこまでも、長く横たわっていました。川の水は、夜の闇を溶かしこんだかのように、深く、重たく見えましたが、その表面には、空の星屑がそのまま映って、ちらちらと光っています。それは、まるで天の川が、地上に倒れてきて、静かに流れているかのようでした。
健一は、草の上にゆっくりと腰をおろしました。そして、両手で膝をかかえながら、じっとその流れを見つめていました。
「自分は、これからどうなってゆくのだろう…」
その思いが、またしても、もくもくと煙のように胸の内に立ちのぼってきました。学校を出たら、どこかで働くのでしょう。そうして、毎日働いて、やがては大人になって、いつかはこの世から消えてゆくのでしょう。それは、この目の前を流れている川の水の一滴が、やがては大きな海へ出て、いつの間にか消えてしまうのと同じようなことではないか、と彼は思いました。
それにひきかえ、空に輝く星たちは、どうでしょう。自分が生まれるずっと前から、いや、人間というものがこの地上に現れる、もっともっと遠い昔から、あの星たちは、あのように変わることなく、涼しい顔をして輝いていたに違いありません。そして、自分が死んで、自分のことなど誰も覚えていないような、遠い未来になっても、やはり同じように、静かに光り続けているのでしょう。
そう思うと、人間の命というものは、なんと小さく、儚いものでしょうか。健一には、それがまるで、夏の夜に一晩だけ鳴いて死んでゆく虫のように、哀れなものに思われたのであります。
その時でありました。健一は、川の向こう岸に、ぽつりと一つ、小さな灯りがあることに気がつきました。それは、建物の灯りにしてはあまりにもか細く、地面に近いところで、まるで蛍がじっと動かずにいるように、またたいています。その黄色く、温かそうな光は、この広い、暗い夜の景色の中で、ただ一つの、生きているものの証のように見えました。
健一は、その光から、どうしても目を離すことができませんでした。いったい、なんの光でしょう。こんな真夜中に、あんな川の岸辺で、誰が火を灯しているのでしょう。彼は、じっと目を凝らしました。すると、その小さな光のそばで、なにか黒い影が、かすかに動いているように見えました。
〜
光は、黄色く、柔らかで、そして、どこか寂しげな光でした。健一は、なんだか、すこし気味が悪いようにも思いました。こんな真夜中に、たった独りで川の岸にいるというのは、まともな人ではないだろう、と思いました。しかし、それよりも、どういうわけか、その小さな光と、そばにいるらしい人物のことが、気になって仕方がなかったのです。それは、この広い、星のまたたく夜の世界で、自分以外に、もう一人、目をさましている人がいるという、不思議な繋がりを感じたからかも知れません。
「橋まで、行ってみよう」
と、健一は自分を奮い立たせるように呟きました。この川の下流の方へ、しばらく歩いてゆけば、古い木の橋があることを、彼は知っていたのです。昼間でも人の渡らない、いたのすき間から川の水が見えるような、頼りない橋でした。
健一は、堤防の草の上を歩きだしました。ざわ、ざわと、彼の足もとで、乾いた枯れ草が鳴りました。それは、まるで夜の静寂が、彼の侵入をささやきあっているかのようでした。ときおり、川の方から、魚のはねる音が聞こえました。そのたびに、健一の心臓は、きゅっと小さくなるのでした。
やがて、彼は橋のたもとに着きました。先を見ると、橋は黒い影となって、向こう岸に伸びています。その向こうには、相変わらず、あの小さな灯りが、またたいていました。
健一は、一度深呼吸をしてから、そろりと橋の上に足を運びました。ふみしめるたびに、古い木の板が、ぎい、ぎいと、頼りない音をたてました。下をのぞけば、暗い水面が、星の光と一緒に健一を吸い込もうとしているかのようです。もし、この橋がこわれて、自分がこの闇の中へ落ちてしまったら、誰が気づいてくれるのでしょう。そんな恐ろしい考えが、ふと頭をかすめました。
やっとのことで向こう岸へ渡りきると、健一は、ほっと一つ、ため息をつきました。そして、今度は、川べりの細い道を、灯りの方へ、ゆっくりと近づいていきました。
だんだん、景色がはっきりと見えてきます。灯りは、ランプのようでした。古風な、金属の檻のついたランプが、どっしりとした石の上に置かれ、あたりを静かに照らしています。そして、その側にうずくまっている黒い影は、腰の曲がった、一人のおじいさんでした。
おじいさんは、そのランプの灯りを頼りに、一心に何かをしていました。健一は、近くにあったツツジの陰に身をかくして、じっとその様子をうかがいました。
おじいさんは、川原の石を、一つ一つ拾っては、手のひらの上で、布きれで丁寧に磨いています。その手つきは、まるで大切な宝物を扱うかのように、どこまでも、どこまでも、静かで、丁寧でした。磨きあげた石を、時々ランプの光にかざしては、満足そうにうなずき、そして、自分のわきに置いてある、小さな袋の中へ、そっとしまっているのでした。
健一には、そのおじいさんのしていることが理解できませんでした。ただの、どこにでも転がっている川原の石です。それを、どうして、こんな真夜中に、たった独りで、あんなに熱心に磨いているのでしょうか。その石は、金や銀に変わるわけでもなければ、何か他に価値のあるものに代わるわけでもないでしょう。
ランプの光に照らされたおじいさんの顔には、深いしわが何本もきざまれていました。しかし、その表情は、不思議なほどに、穏やかでした。まるで、この世のどんな悲しみも、悩みも、全てを忘れて、ただ、目の前の石とだけ向き合っているようでした。その姿を見ているうちに、健一の胸を抑えつけていた、あの重たい石のようなものが、ほんの少しだけ、軽くなるような気がしたのです。
健一は、息を殺して、その不思議な光景を、じっと見つめていました。おじいさんは、いったい、何のために、あんなことをしているのでしょう。そして、あの小さな袋の中には、今まで磨きあげた、どれほどの石が、入っているのでしょう。
健一は、息を殺したまま、葉のあいだから、じっとその光景に見入っていました。おじいさんの背中は、夜の闇に溶けてしまいそうに小さく、丸まっていました。しかし、その手もとで、熱心に石を磨いている姿は、なにか大きな、動かすことのできない岩のように、どっしりと落ち着いて見えました。
どのくらいの時間が、そうして過ぎていったのでしょうか。川のせせらぎと、時折、草むらで虫のなく声のほかには、なにも聞こえませんでした。健一の胸をいつもおさえていた重たい石は、この静けさの中にいるうちに、いつのまにかその角がとれて、少しばかり丸くなったような気がしました。
〜
その時、おじいさんが手を止めました。そして、磨いていた石をそっと膝の上に置くと、ゆっくりと顔をあげて、健一が隠れている、こちらの草むらを、じっと見たのです。
健一の心臓が、どきり、と大きくはねあがりました。見つかってしまった、と思ったのです。怪しまれているのでしょうか。それとも、叱られるのでしょうか。健一は、身を固くして、どうすることもできずに、ただじっとしていました。
しかし、おじいさんは、なにも言いませんでした。その顔には、驚いたような表情も、怒ったような表情もありません。深いしわのきざまれたその顔は、まるで、そこに健一がいたことなど、はじめからすっかり知っていたかのように、穏やかでした。その目には、遠い昔のことを思い出しているような、懐かしいやさしさが宿っていたのです。
健一は、もう、そこに隠れていることが、できなくなってしまいました。それは、まるで、暖かい日の光に誘いだされた、春の虫のようでした。彼は、そろそろと草むらから姿を現して、おじいさんの前へ、ゆっくりと進み出ました。
「…こんばんは」
それだけ言うのが、精一杯でした。声は、自分でもおかしいと思うほど、かすれていました。
「おお、そこにいたのかね」
と、おじいさんは、やさしい声で言いました。そして、にこりと笑いました。その笑った顔は、しわだらけでしたが、不思議なほど、温かく感じられました。
「こんな夜ふけに、若い者が、どうなされたかな」
「眠れなくて…それで、すこし、歩いていました」
「そうか、そうか。わしもな、夜になると、どうも目がさえてしまって、いけなくてな。こうして、川の音でも聞きながら、友だちと話をするのが、なによりの楽しみなのじゃよ」
友だち、と聞いて、健一は、あたりを見まわしました。しかし、この川原には、おじいさんと、自分と、そしてランプの小さな灯りのほかには、何もありません。
健一が、不思議そうな顔をしているのを見て、おじいさんは、またしわだらけの顔で笑いました。そして、膝の上の石ころを、そっと手のひらの上にのせて、健一の方へ差しだしました。
「この子じゃよ、わしの友だちというのは」
それは、どこにでもころがっている、なんの変哲もない、丸い石でした。ただ、長く磨かれていたせいか、ランプの光をうけて、しっとりと濡れたように、鈍い光を放っています。
「石が…友だち、ですか」
「そうじゃ。わしはな、こうして夜の間に、この友だちを一人ずつ、きれいにしてやるのじゃ。そうするとな、昼間には見えなかった、美しい模様が浮かんでくることがある。ただ黙って、じっとわしの話を聞いてくれる。それだけで、わしの心は、ずいぶんと、楽になるのじゃよ」
おじいさんは、そう言うと、また布きれを取りだして、その石を、愛おしむように、そっと撫ではじめました。その静かな手つきを見ていると、健一には、本当に、その石が、耳を傾けてくれているかのように思えました。
「この石ころにもな、一人一人、顔があり、心がある。おまえさんには、ただの石ころにしか見えんじゃろうが、わしの目にはな、みんなちがって見える。長い、長いこと、この川の底で、水の流れに身をまかせて、他の石とぶつかりあって、そうして、こんなに丸うなったのじゃ。うれしいことも、かなしいことも、みんな、この身体にきざんでおる。わしら人間と、どこか、似てはおらんかな」
おじいさんの言葉は、健一の胸の内に、ぽつり、ぽつりと、温かい雨の雫のように、しみこんでいきました。自分を苦しめていた、あのわけのわからない悲しみも、悩みも、このおじいさんにとっては、石ころが川底で転がっているのと同じような、自然なことなのかも知れない、と彼は思いました。
ふと見ると、東の空の、山の稜線にそったあたりが、いつのまにか、墨色から、少し明るい灰色に変わっていました。夜明けが、もうすぐやって来るのです。
〜
「わしはな、若いころ、おまえさんのように、ずいぶんと、思い悩んだものじゃ。なぜ、自分はこんなに苦しまねばならんのか。なぜ、世の中は、自分の思うようにならんのか、とな。まるで、心の内に、角のある、ごつごつした石が、一つ、入っておるようじゃった。しかしな、決してその石を壊してはならんと思った。そのかわりに、時間をかけて向き合った。ながい、ながい、時間をかけたのじゃ」
おじいさんは、そう言うと、先ほどまで磨いていた石をよく見せてくれました。それは、丸くて、白い筋が、何本も走っている、不思議な模様の石でした。
「ごらん。この石などは、まるで、わしの顔のしわのようじゃろう」
と、おじいさんはいたずらっぽく笑いました。そのしわだらけの笑顔を見ていると、健一にも、いつの間にか、かすかな笑みが浮かんでいました。こんなふうに、心から穏やかに笑ったのは、いったい、いつ以来のことでしょう。
やがて、東の空は、ねずみ色から、うすい紅色へと、静かにその色を変えていきました。対岸の木々の黒い影が、はっきりとその輪郭を現しはじめ、川の水面には、朝の光が、金色の粉をまいたように、きらきらと輝きはじめました。夜の間に、あれほど冷たく、重く見えた川が、まるで新しい命をあたえられたかのように、生き生きと流れだしました。
おじいさんは、名残惜しそうに、手に持っていた石を磨きあげると、それを足元に置き、ゆっくりと立ちあがりました。そして、ランプの火を、ふっと吹き消しました。すると、あたりは急に、朝のすがすがしい光に満たされました。
差し込んだ朝陽に、思わず健一は目をつむりました。明るくなった視界に目を馴染ませるように、おそるおそる目を開いた時には、もうおじいさんの姿はありませんでした。
あとには、健一と、磨かれた石ころだけが、残されていました。
おしまい
スポンサーリンク
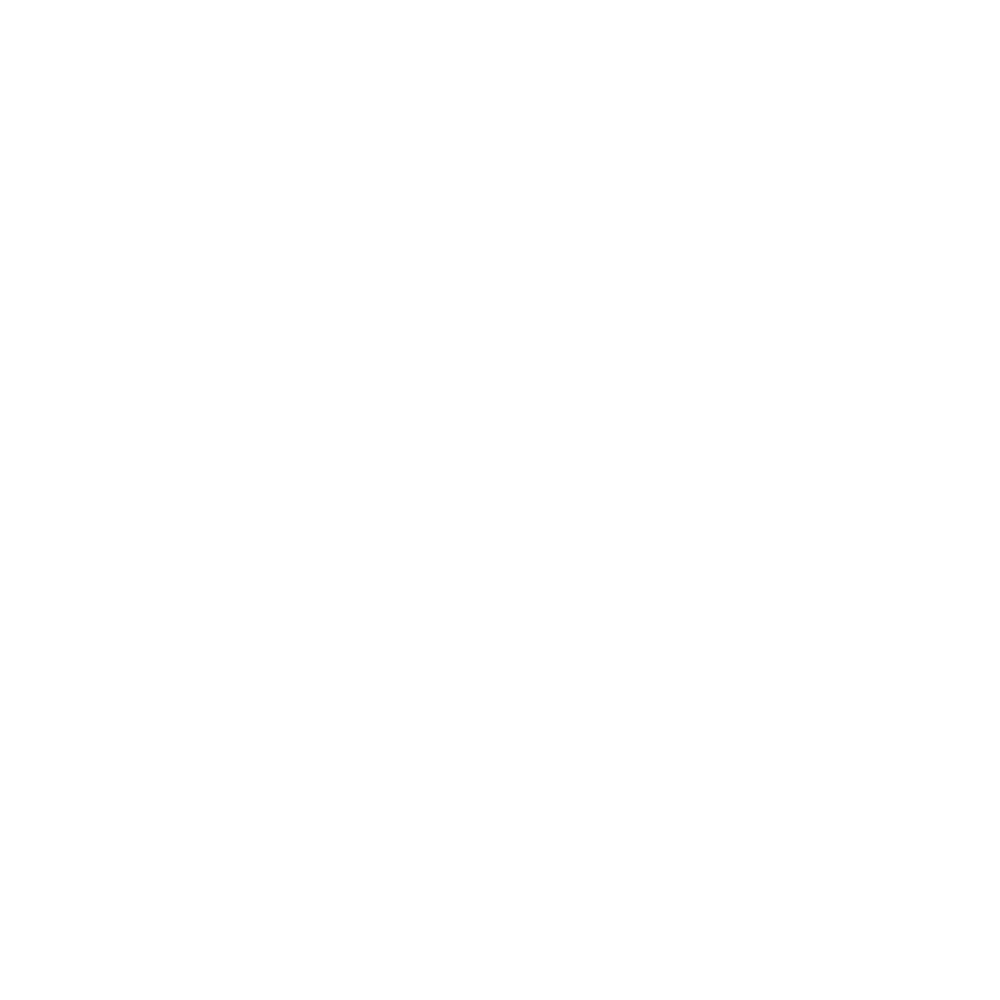










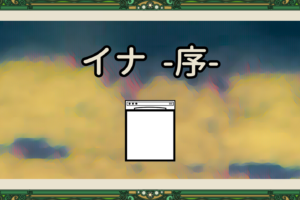
最近のコメント