浦島太郎
夜咄 頼麦 作
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この文章の著作権は夜咄頼麦に帰属しますが、朗読についての著作使用権は解放しております。YouTubeでの朗読、声劇、そのほか音声表現活動などで自由にお使いください。
その際、この原作ページのURLを作品などに掲載していただきますよう、お願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
むかしむかし、海のそばの小さな村に、浦島太郎という心やさしい漁師が住んでいました。太郎は年老いたお母さんと二人きりで暮らしていて、毎日海に出ては魚を釣って、村の人々に分けてあげていました。太郎は、とても親孝行な青年でした。
ある日のことです。太郎が浜辺を歩いていると、子どもたちが何かを囲んで騒いでいるのが見えました。近づいてみると、小さな子ガメが砂の上でひっくり返って、困っているではありませんか。子どもたちは面白がって、棒でつついたり、子ガメに向かって石を投げたりしています。
「こら、そんなことをしてはいけませんよ」
太郎は子どもたちを優しくたしなめると、そっと子ガメを手に取りました。子ガメの小さな目には、涙が光っていました。
「大丈夫ですよ。すぐに海へ帰してあげますからね」
太郎は子ガメを波打ち際まで運び、海の水に浸かる場所にそっと置いてあげました。子ガメは太郎を振り返ると、まるでお礼を言うように小さく頭を下げて、海の中へ泳いでいきました。
それから三年の月日が過ぎました。
太郎は相変わらず、お母さんと二人で静かに暮らしていました。お母さんは体が弱くなってきましたが、太郎の作る魚料理を美味しそうに食べて、いつも穏やかに微笑んでいました。
ある日の夕暮れ、太郎がいつものように海で釣りをしていると、ざぶーりざぶりと波が立ちました。そして、その波の間から、美しい甲羅を持つ大きな亀が現れたのです。
「浦島太郎さま、覚えていらっしゃいますでしょうか」
亀は太郎に向かって話しかけてきました。太郎はとても驚きましたが、亀の優しい目を見ていると、不思議と心が落ち着いてきました。
「私は三年前に、あなたに助けていただいた子ガメでございます。あの時のご恩をお返しするため、竜宮城の乙姫さまがお呼びでございます」
太郎は戸惑いました。竜宮城なんて、おとぎ話の中だけの世界だと思っていたからです。でも、亀の真剣な表情を見ていると、断るのも悪いような気がしてきました。
「でも、お母さんが一人になってしまいます」
「ご心配なく。お母様には海の幸を届けさせましょう。太郎さんのことも、すぐにお帰しいたしますから」
太郎は少し迷いましたが、結局亀の背中に乗ることにしました。
海の中は、太郎が想像していた以上に美しい世界でした。色とりどりの魚たちが泳ぎ、珊瑚礁が虹色に光っています。水面から差し込んだ光が、まるで風になびく絹織り物かのように揺れ、太郎の身体にも水影を映しました。
やがて、宮殿のような美しい建物が見えてきました。壁面は美しい貝殻や珊瑚で飾られ、すべてがきらびやかに輝いています。それが竜宮城だったのです。
竜宮城では、美しい乙姫さまが太郎を温かく迎えてくれました。乙姫さまの周りには、タイやヒトデ、ヤドカリやクラゲなど、たくさんの海の生き物たちがいて、みんな太郎を歓迎してくれました。
「浦島さま、あの小さな亀を助けてくださって、ありがとうございました。心より御礼申し上げます」
乙姫さまは美しい声で言いました。
「お礼に心ばかりのおもてなしをさせてください」
それからというもの、太郎は毎日、竜宮城で楽しい時間を過ごしました。魚たちが踊りを踊ってくれたり、美しい音楽を聴かせてくれたり、見たこともない美味しい料理をいただいたり。太郎は生まれて初めて、こんなに贅沢で楽しい毎日を送りました。
でも、だんだんと太郎の心に、小さな影がさしてきました。お母さんのことが気になって仕方がないのです。お母さんは一人で大丈夫だろうか。寂しい思いをしていないだろうか。そんなことを考えると、美しい音楽も、美味しい料理も、心から楽しめなくなってしまいました。
乙姫さまは、そんな太郎の様子にすぐに気がつきました。
「浦島さま、何か心配事がおありですか」
太郎は正直に、お母さんのことを話しました。すると乙姫さまは、優しく微笑みました。
「そのようにお優しい方だからこそ、あの子ガメを助けてくださったのですね。分かりました。お母様のもとへお帰りください」
乙姫さまは太郎に、美しく飾られた小さな箱を手渡しました。
「これは玉手箱と申します。もし何か困ったことがございましたら、お開けください。きっとお役に立つでしょう」
太郎は乙姫さまと海の仲間たちに別れを告げ、再び亀の背中に乗って村へ帰りました。
ところが、亀に別れを告げたあと、村に着いてみると、太郎は目を疑いました。自分の家があったはずの場所は、草の生い茂る空き地になっています。村の様子も、すっかり変わってしまっていました。そして何より、太郎の知っている人が一人もいないのです。
太郎は慌てて、堤防に座っていた村の人に尋ねました。
「すみません、浦島太郎という漁師をご存知ありませんか」
「浦島太郎?ああ、昔そんな名前の人がいたと、お爺さんから聞いたことがあります。でも、それはもう百年も前の話ですよ」
太郎は愕然としました。竜宮城で過ごしたのはほんの数日だと思っていたのに、この世界では百年もの時が流れていたのです。お母さんは、もうこの世にはいませんでした。
太郎は悲しみに打ちひしがれ、自分の家があったはずの空き地に座り込んでしまいました。たしかに竜宮城での時間は楽しいものだった。でも、それと引き換えに失うものがあまりに大き過ぎるじゃないか。こんなことなら、贅沢な暮らしじゃなくていい。お母さんといつまでも穏やかに暮らしていたかった。
太郎は、ふと乙姫さまからもらった玉手箱のことを思い出しました。そういえば、困った時にこの箱を開けるようにと言われていたのでした。
太郎は、箱についていた金具を外しました。恐る恐る箱を開けると、中から白い煙がもくもくもくと立ち上りました。煙は太郎を包み込み、たちまち太郎の髪を真っ白に変えてしまいました。それだけではなく、みるみる身体にはしわが刻まれ、腰は曲がっていきます。
「ああ、私までお爺さんになってしまうのか」
太郎は悲しみのどん底で膝をつき、目をぎゅっとつむり、頭を抱えてうずくまってしまいました。
どのくらいの時間が経ったのでしょう。
うずくまったままの太郎の耳元に、懐かしい声が聞こえてきました。
「太郎や、よく帰ってきましたね」
太郎が顔を上げると、そこには、あの頃のお母さんが立っていました。辺りは、百年前の村の姿に戻っています。気づけば、自分の身体まで若い姿に戻っていました。
「お母さん!」
太郎は、目に涙を浮かべながら、優しく微笑む母の顔を見つめました。
「私はずっと、太郎の帰りを待っていましたよ。海の幸よりも何よりも、あなたに会える日を楽しみにしていたわ」
太郎とお母さんは、久しぶりに抱き合いました。
「太郎や、あなたは立派に生きてきました。生き物を大切にする心、人を思いやる心、それらは決して無駄ではありませんでしたよ。さあ、土産話を聞かせておくれ」
太郎はお母さんと村の人々に囲まれて、自分の不思議な体験を話して聞かせました。最初は皆、驚いていましたが、太郎の優しい人柄と、穏やかな口調に、だんだんと語られた海の世界を思い描きました。
その後も、太郎は村で一番の物知りとして、子どもたちに昔話を聞かせたり、生き物の大切さを教えたりしました。そして時々、海辺に立って水平線を眺め、竜宮城での生活を思い出しました。太郎はお母さんと、村の人々と一緒に、いつまでも仲良く暮らしましたとさ。
おしまい
スポンサーリンク
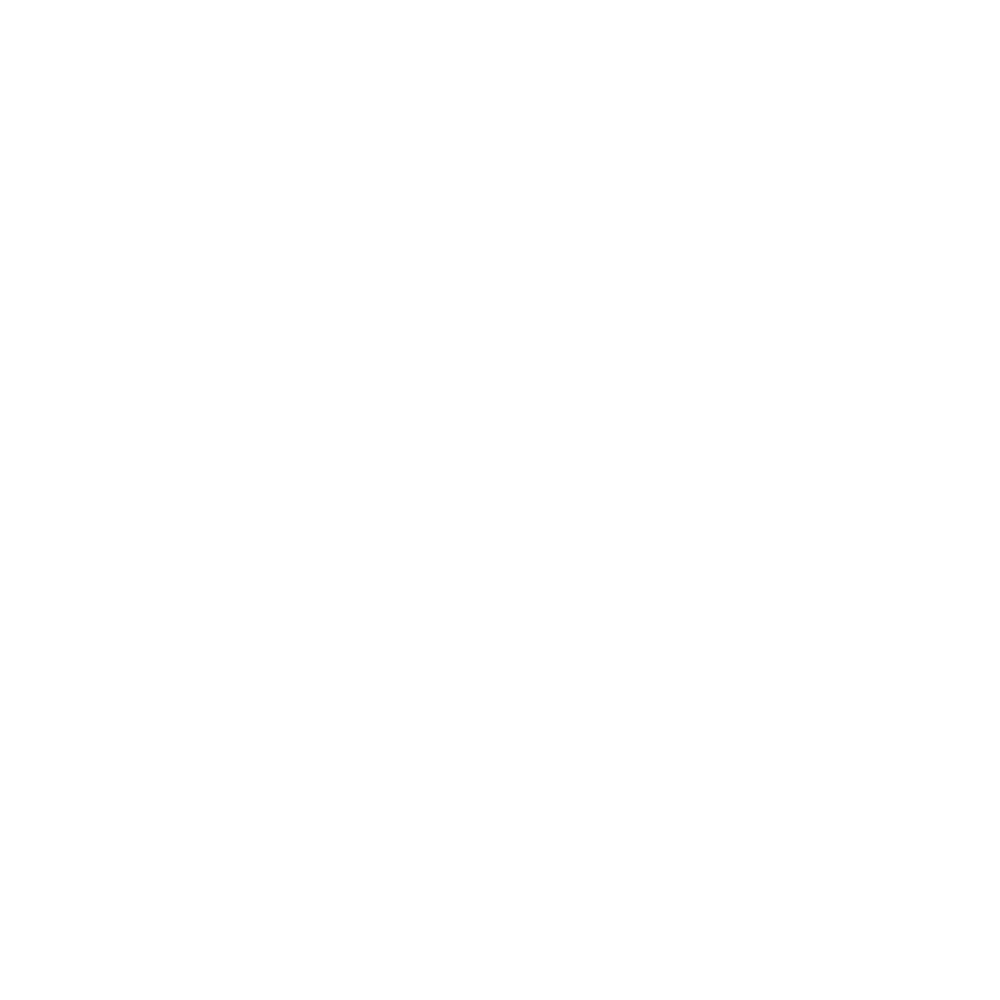
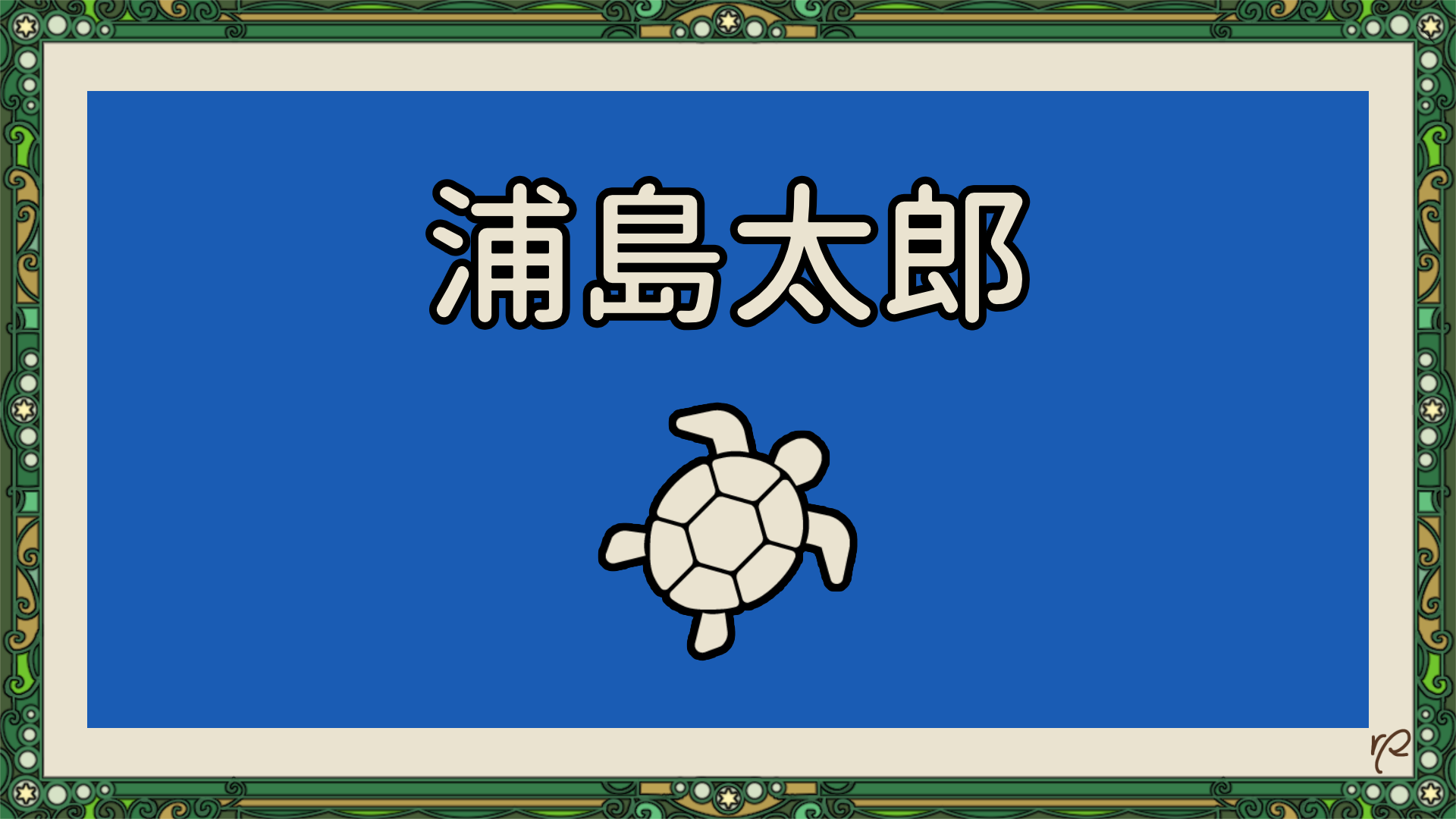










最近のコメント