キジも鳴かずば
夜咄 頼麦 作
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この文章の著作権は夜咄頼麦に帰属しますが、朗読についての著作使用権は解放しております。YouTubeでの朗読、声劇、そのほか音声表現活動などで自由にお使いください。
その際、この原作ページのURLを作品などに掲載していただきますよう、お願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
むかし、むかし、山にはりつく小さな村のそばに、犀川というとても大きな川が流れていました。
この川は、毎年の秋に大雨が降ると氾濫して、村の田んぼや畑を水びたしにしていました。村の人々は、そのたびに困って空をあおぎ、川の流れが元通りになるように祈るばかりでした。
この村に、弥平という心のやさしい父親と、お千代という小さな娘が、古びた家に二人きりで暮らしていました。弥平は毎日まじめに働いていましたが、貧しくて、その日その日を生きるのがやっとでした。
ある年の秋のことです。お千代は重い病気にかかってしまいました。熱が出て、体がふるえて、起き上がることもできません。弥平はお千代の小さな手をにぎって、「お千代、がんばるんだよ」とくり返しました。
けれど、貧しい家には、お医者さまを呼ぶお金もありません。弥平は村中をかけまわって、薬草をあつめました。近所の人に頭を下げて、おかゆを分けてもらいました。それでも、お千代の病気はよくなりませんでした。
ある晩、お千代が小さな声で言いました。
「父ちゃん…あずきまんまが食べたいな…」
あずきまんまというのは、小豆とお米をいっしょにたいたごはんのことです。お千代は、むかしに一度だけ、村のお祭りの日にあずきまんまを食べたことがありました。その時の、あたたかくて、ほんのりあまい味が、お千代の心に残っていたのです。
弥平は、こぼれそうになる涙を必死にこらえました。大切なお千代の頼みですが、小豆を買うお金なんて、一文もありません。
「お千代…すまない…」
弥平は、その夜、眠ることができませんでした。娘のやせた寝顔を見ていると、心がしめつけられるようでした。そして、とうとう、おそろしいことを考えてしまったのです。
夜が更けたころ、弥平は、村長さまの家の倉に、こっそりと忍び込みました。そして、小豆とお米を、ほんの少しだけ、ふところに入れて持ち帰ったのです。弥平の手は、ふるえていました。心の中で、「ごめんなさい、ごめんなさい」と、何度もくり返しながら、弥平は家に帰りました。
次の日の朝、弥平はすぐに、あずきまんまを炊きました。小豆の紅い色とお米の白い色がまじって、とてもきれいでした。ゆげが立ちのぼって、いいにおいがしました。
「お千代、できたよ」
お千代は、小さなお茶わんに入ったあずきまんまを、口いっぱいにほおばりました。そして、涙をこぼしながら言いました。
「おいしい…父ちゃん、ありがとう…」
その日から、お千代の熱は下がりはじめました。もう何日かすると、お千代はすっかり元気になって、また外で遊べるようになりました。弥平は、心から安心しました。
ある日、弥平が仕事に出かけたあと、お千代は家の前で手まりをついて遊んでいました。手まりがぽんぽんとはずむたびに、お千代は歌を歌いました。
「てんてん手まり、てん手まり。あずきまんまたべた、おいしかった」
お千代は、うれしくて、うれしくて、何度もくり返し歌いました。しかし、近所の人に、その歌を聞かれたことがいけませんでした。
その夜から、また雨がはげしくなりました。ざあざあと、まるで天から滝の水が落ちてくるようでした。犀川の水は、ごうごうとうなり声をあげて、あふれそうになりました。
村の人たちは、村長さまの家にあつまって、相談をしました。
「このままでは、また村が水びたしになってしまう」
「このような時には、つみをおかした者を村から追放し、川にささげるべしと言いつたえられている」
「しかし、つみをおかしたものなど、この村にいるだろうか」
そこで、ひとりの男が思い出したように言いました。
「そういえば、お千代ちゃんが、あずきまんまを食べたと歌っていた。あの貧しい家に、小豆を買うお金があるとは思えない」
村の人たちは、顔を見合わせました。そして、弥平が村長さまの倉から、ぬすみを働いたことに気がついてしまいました。
その夜のうちに、村のお役人が弥平の家にやってきて、弥平をつかまえました。
「おまえは、ぬすみをしたな。村の掟により、おまえを村から追放する」
弥平は、何も言いかえすことができませんでした。ぬすみをしたことは、本当のことだったからです。
弥平は、大雨の中を、川の方へ引き立てられていきました。
「父ちゃん!父ちゃん!」
泣きさけぶ、お千代の声は、雨の音にかき消されてしまいました。
お千代は、もう父ちゃんには会えないことを悟りました。そして、くる日もくる日も泣き続けました。しかし、ある日ぴたりと泣きやんで、一言も口をきかなくなってしまいました。
村の人たちは、さすがにお千代をかわいそうに思って、代わるがわる、ごはんを持ってきてくれました。でも、お千代は、ごはんにはほとんど手をつけず、ただうなだれるばかりでした。
そして、お千代は、とつぜん家からいなくなってしまいました。村じゅうの人々が辺りを探しましたが、手がかりもなく、どこかへ消えてしまったのです。
そのまま、何年かが過ぎました。
ある日、村の猟師が山を歩いていると、空高く舞うキジの美しい鳴き声が聞こえました。猟師は鉄砲をかまえ、キジに向けて引き金をひきました。
キジは悲しい声をあげて、地面に落ちました。
猟師がキジの落ちたあたりにかけよってみると、なんと、一人の娘がキジをだきかかえていました。それは、白い着物をまとった、お千代でした。
「おまえさんは、お千代ちゃんじゃないかい」
お千代はその言葉には答えず、キジをやさしくなでながら、しずかにつぶやきました。
「キジよ、おまえも鳴かなければ、撃たれないですんだのよ…」
その声には、深い悲しみが宿っていました。
猟師の前で、お千代はそっと、キジの傷口に手をかざしました。すると、ふしぎなことに、傷がみるみる癒えていくではありませんか。
やがてキジは元気に立ち上がり、一声も鳴かずに、静かに空へ飛びたちました。青い空に、その姿が小さく、小さくなっていきます。
猟師は思わずその姿を目で追っていましたが、ふと気づいてお千代のほうへ目をもどしました。
しかし、そこにはもう、だれもいませんでした。その代わりに、少し先の木立を、手をつないだ二人の影が去っていくように見えました。
それからというもの、どうしたことか、犀川は、もう氾濫することがなくなりました。どんなに雨がふっても、川の水は村を守るように、やさしく流れるようになりました。
村人たちは、追放した弥平と、いなくなったお千代のことを思い、犀川のほとりに小さなほこらを建てました。
そのほこらには、秋になると毎年、決して鳴くことのないキジが一羽、静かにたたずんでいるそうです。
おしまい
スポンサーリンク
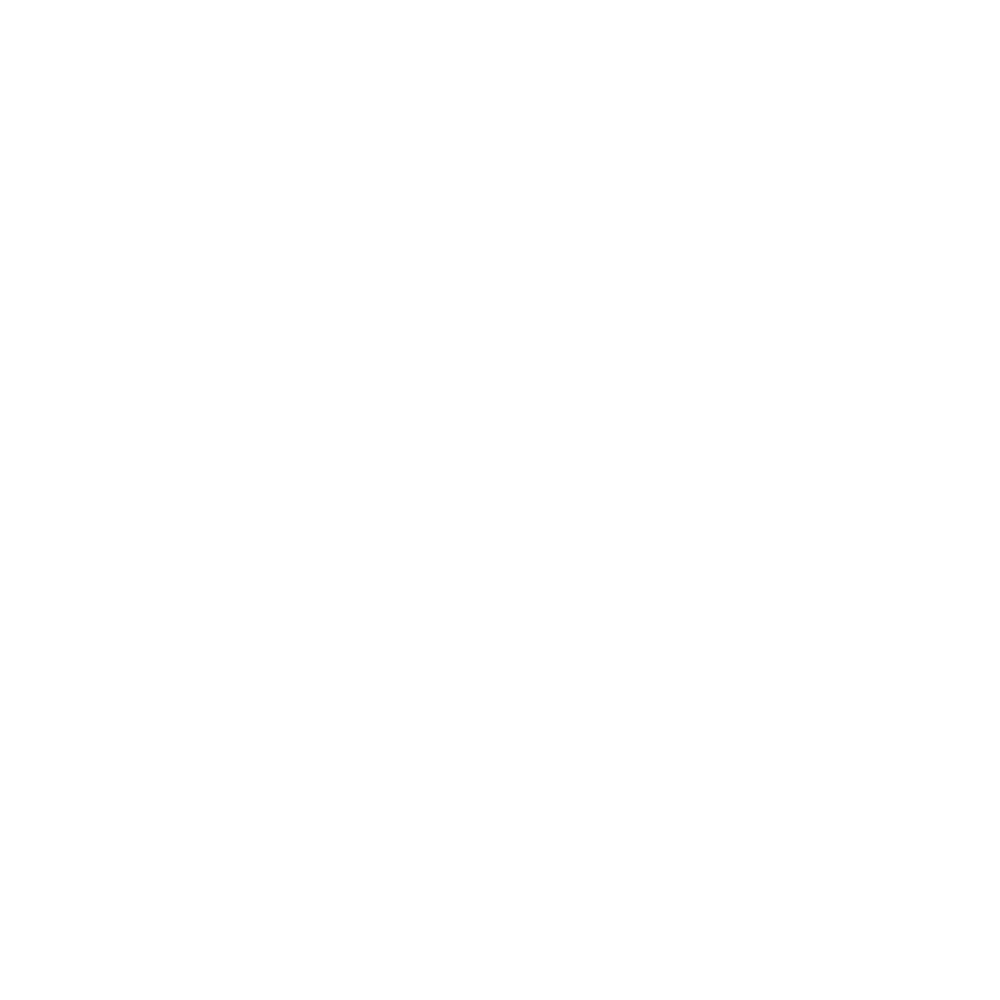











最近のコメント